自分のメリットだけを優先して話す人とは、気づくと距離を置いている。
性別、年齢、立場問わず。相手にとって”私”という個人はそもそもいない上での会話だからだ。
都合のいいように相手は接してくる。その意図を感じたとき、私はその相手から離れ、できるだけ関わりたくないと思いはじめている。次はどうやってかわそうか、と考えている。
自分のその思考は卑屈すぎる…、と思い悩むこともある。相手はそんなつもりはないのではないかと、自らの猜疑心を否定するのだが、それが無駄であったりする。
人の善意を食い物にする人間は存在する。相手はそんなことすら思ってもいないし、振り返ることはないだろう。そして、目と口でものを言い、それに伴う行動は、自分しか見ていない証拠となって私を襲ってくる。
アーシュラ・K・ル=グィン『オメラスから歩み去る人々』
少々過激な文章になりつつある。。。いや、これが過激なのか?
鏡のように同じ振る舞いで返してあげたいと思う。しかし私にはそれができない。勇気がない。
せめてできる抵抗は、その相手から遠ざかっていくことだ。
通勤時の車の中で、延々と自問自答したりするのだが、最善の答えはいっこうに出てこない。堂々巡りだ。こういった気持ちが発生するとき、決まってアーシュラ・K・ル=グィンの『オメラスから歩み去る人々』を思い出す。短い物語なのだが、その世界は麻痺したこの世界と似ていて、恐ろしいほど現実的である。

ある意味では本能的でもあるのだろうが、虐げられている存在がいるということを意識するだけでも、世界の見え方は変わる。
『オメラスから歩み去る人々』と私の状況とは、まるで違う設定ではあるのだが、誰かを利用すれば、その享受を得られるという点において同じように思う。きっとこの先も似たような状況と関わりが待っているだろう。その都度、「オメラス」を思い出すだろうし、その都度、私はやりきれない気持ちになるのだろう。
綺麗事ではなく、その場から去るしかできない選択もある。それでいいのだろうか、などと問いながらも、去ってしまう自分がいる。
他方で、人間のそれは普遍的にもなっていて、多様な感情を相互に持つことは自然でもある。だからこそ詩や文学などの芸術が生まれるようにも思う。だとしたら、だからこそ、私を捉えて離さないのかもしれない。

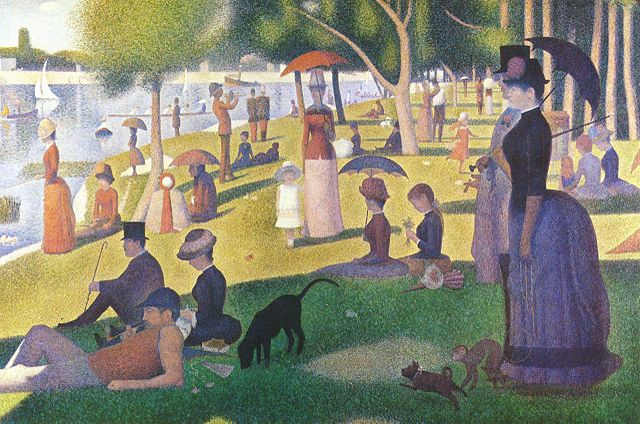

Comment